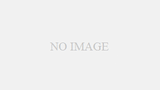アメリカザリガニは、アメリカ大陸南部のミシッシピ川流域原産のザリガニで、昭和 2 年に食用として輸入されたウシガエルの餌として日本に持ち込まれて以降、日本各地に分布を広げています。
アメリカザリガニは、子ども達からも親しみやすい生き物として認識され,一般家庭や学校等でも普通に飼育が行われており,水路や川などで採集する生き物としての人気も非常に高い生き物です。
しかし、その反面アメリカザリガニは、日本各地で生態系に大きな影響を及ぼしていることから、環境省によって「要注意外来生物」に指定されたのちに、2023年6月には「条件付特定外来生物」に指定をされ、飼育は出来るものの売買や放流に罰則が付くようになりました。
また、日本生態学会の「日本の侵略的外来種ワースト 100」にも選定されています。
アメリカザリガニはなぜ駆除をしないといけないのか?

アメリカザリガニが定着した、ため池などの水域では水草が全て食べ尽くされ、トンボの幼虫でもあるヤゴやゲンゴロウなど水生昆虫が減少、全滅する事例が報告されています。
アメリカザリガニの天敵でもあるブラックバスの駆除後のため池などでは、アメリカザリガニが大繁殖し水生昆虫が全滅する事例が増えており、生態系全体を保全する立場からブラックバスのみを駆除する事にを疑問視する人もいます。
しかし、日本に本来生息する魚類を保全するためにはブラックバスの駆除が必要不可欠であり、ブラックバス駆除を今後も継続するためにはアメリカザリガニなど侵略的外来種を総合的に駆除しなければなりません。
アメリカザリガニの被害
アメリカザリガニによる被害は、大きく分けて3つあります。
1,在来種への直接的な影響
2,在来種への病気の媒介
3,農業被害
アメリカザリガニが定着している水域でも、駆除したことにより、水生生物の生息数が劇的に回復した事例が報告されています。
1,在来種への直接的な影響
水生植物
アメリカザリガニが定着した、水域では水生植物の減少が多くみられるだけではなく、その水域に自生していた在来種の水生植物が完全に姿を消してしまった事例も少なくはありません。
一方、アメリカザリガニの駆除を積極的に行っている水域では、抽水植物やミジンコのような動物プランクトンが増加がみられたと言う報告が、あるものの完全に駆除が出来ていないため、沈水植物の増加までには至っていないとのことです。
水棲昆虫
アメリカザリガニが未定着のため池ではゲンゴロウ類等の希少昆虫を含む20種類以上の水生昆虫が確認された一方で、同じ地域のアメリカザリガニが高密度で確認されたため池ではわずか3種類しか水棲昆虫の確認が出来なかったとのことです。
また、別の地域では全国的に唯一安定したある水棲昆虫の産地が存在したが、アメリカザリガニの侵入により産地の多くが絶滅状態となっており、現在はその水棲昆虫の確認例はありません。
魚類
室内での実験の結果、メダカやタナゴなどの魚もアメリカザリガニに捕食されると言う結果が出ていますが、底生性のドジョウがもっともアメリカザリガニに捕食されやすいという結果が出ています。
また、捕食による被害だけではなく二枚貝などに産卵するタナゴ類の産卵母貝への食害の影響として、アメリカザリガニが二枚貝を食害した結果、産卵場所(産卵母貝)を失ったタナゴが消失したとされています。
両生類
両生類が生息する水域でアメリカザリガニの侵入が確認されたのちに、ヤマアカガエルやアズマヒキガエルと言ったカエル類、サンショウウオなどの卵塊の破壊が確認されています。
また同時に、怪我をしている両生類、生息している両生類の減少も確認され、アメリカザリガニによる捕食も行われているとされています。
2,在来種への病気の媒介

アメリカザリガニが媒介するとされるザリガニペスト(アファノマイシス菌)によるニホンザリガニへの感染リスクがあります。
このザリガニペストはニホンザリガニに感染した場合の致死率が高いとされ問題視されています。
ニホンザリガニが生息する、ニホンザリガニの大量死亡が観察され、死亡要因を分析したところ、ザリガニペストに感染したことが明らかとなりました。
さらに遺伝子解析の結果、アメリカザリガニが保菌していたザリガニペストに由来している可能性が高いことが判明されています。
ニホンザリガニとアメリカザリガニの生息域が重複していませんが、アメリカザリガニを捕獲した網やそのとき直用していたクツや長靴にもザリガニペストの菌が付着し、それを持ってニホンザリガニが生息している水域に侵入することで、ニホンザリガニがザリガニペストに感染するともぃわれています。
また、甲殻類に広く感染することが知られる白斑病の媒介リスクもあり、中国ではエビの養殖池に隣接した天然河川で捕獲されたアメリカザリガニの99%が白斑病に感染していることが報告があるとされています。
3,農業被害
水田では、アメリカザリガニが巣穴を掘ったことが原因で漏水が発生し、その修復に労力を要しています。
また、この漏水により除草剤の効果が薄れ雑草が繁茂し、その結果米の収穫量が減少する事例も発生しています。
このような農業被害により耕作放棄が発生する恐れも懸念されています。
まとめ
筆者自身も飼育していますが、アメリカザリガニは、子ども達からも親しみやすい生き物として認識され,一般家庭や学校等でも普通に飼育が行われており,水路や川などで採集する生き物としての人気も非常に高い生き物です。
しかし、その反面在来種への直接的な影響、在来種への病気の媒介、農業被害などがあるのも事実です。
我々に出来る事は、アメリカザリガニの日本の生態系への影響を理解し、飼育している場合はアメリカザリガニを逃がさないこと。
可能であれば、野生のアメリカザリガニの駆除活動などへの参加でしょうか。
また、アメリカザリガニは加害者ではなく、望んでもいないのに人間によって勝手に日本に連れてこられた被害者です。
このような被害者を増やさないよう、飼育している生き物を野外に放つことなどは絶対にしないでください。